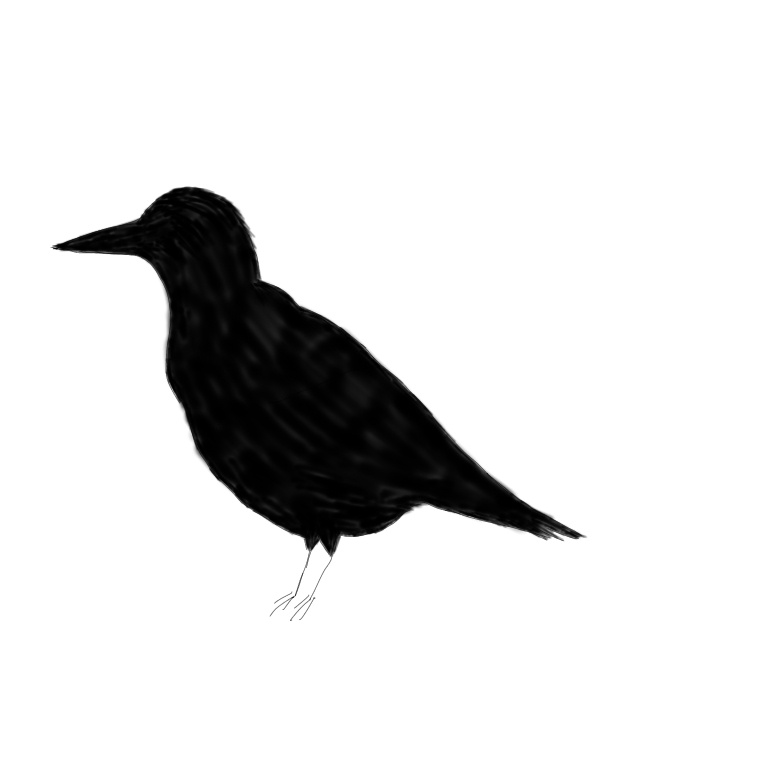「同じ骨」
【お題】
起:主人公が目を覚ますと、変身していることに気付く。
承:変身したことでいろいろある。
転:ある存在と出逢い、プレゼントを受け取る。
結:変身が解ける。
朝目を覚ましたら、掃除のおばさんになっていた。
いや、外見年齢は変わっていなかったが、なんだろう、この「おばさん」と言ってしまうのは。人間の言葉というやつはときどき不思議だ。
それにしても、そうか、今日は清掃員か。
私は日毎にいろんなものになる。清掃員、料理人、販売員──この街でその日に求められている職業になる。
私は、なりたいものにはなれない。
なりたいものなんてものを、そもそも私の頭は考えないのだけれど。
私はドールと呼ばれるヒューマノイドだ。
この思考はどこかの誰かがプログラミングした人工知能によるものだし、この身体はどこかの誰かが作った生物ではない何かで、日毎いろんな職業に扮する。
様々な施策にも人口減少はとどまるところを知らず、やがて人間は人間の少なさを補うためにヒューマノイドを作り出した。人間では手が回らないあれこれを行わせるために。ドールも初めは各個体がそれぞれの職種を持っていたが、やがて日毎にリセットする機能が開発され、毎日、その日の需要に応じた仕事が割り振られるようになった。その方が、職業分のドールを用意しておくよりも効率がいい。
昨日も、今日も、明日も、私はドールとして求められた職業になる。
私は、なりたいものにはなれない。
通りの落ち葉を掃く。一箇所に集め、袋に詰めて、焼却場へ運ぶ。
ゴミは少ない。
人間の少ない街では、ゴミも少ないということなのだろう。
様々な仕事がドールに任されるようになり、悠々自適に暮らす人間たちはそれでもなおその数を減らしていった。いろんなことがドールで済んでしまい、人間でなくてもよくなってしまったのかもしれない。ドールが各種の仕事を担うようになってからそう経たない内に世界では、人間よりもドールの方が圧倒的に多くなった。
それからも人間の数はどんどんと減っていき、すでに、いくつもの街が、国が、人間がいなくなって消滅した。
この街でも、今やごく僅かになった人間たちは、ドールたちの世話を受けながら、ゆっくりと終わりへ向かっている。
掃除している間、通りがかった人間は近所に住む老人一人。人間は本当に少なくなった。
通りの後は、とあるご老人の家の掃除だった。
人間が少なくなってゴミは減ったけれど、少ないといえゴミは出るし掃除はいる。一時期、いろいろなこと──掃除や洗濯や料理など主に家事──が機械化・自動化されたらしいけれど、それらの機械をメンテナンスして維持していくよりも、様々な職業をこなせるドールの方が効率がよかったらしい。機械たちは今や埃を被って眠っている。
その家にはおじいさんが一人で住んでいた。もっとも、今この街に老人でない人間はいないし、一人暮らしでない人間もいないのだけれど。
おじいさんは、「よく来たね」とにこやかに私を迎え入れた。
それほど大きな家ではなく、特にゴミが多かったり汚れていたりするわけでもなく、全く散らかっていない家の掃除が一時間もかからずに終わってしまうと、おじいさんは私にお茶を勧めてくれた。
「時間はまだいいだろう、少し、私のお茶に付き合ってくれんかね」
断る理由はない。依頼主──と言って差し支えないと思う、この場合は。きっとこのおじいさんが自分の家を掃除してほしいと思ったから、今日私がここに清掃員として来たのだろうから──とお茶をする、というのは、仕事ではないが、大きく逸脱するわけではない。ドールは街の共有物だから、誰かと個人的な関係を結ぶことは良しとされないけれど、仕事の後にお茶をご馳走になるくらいであれば構わない。人間ではなくヒューマノイドなのに、所詮は機械なのに、人間のように食べたり飲んだりできるし眠ったりもするこの身体は我ながらおかしい。
「もう少し早くしたかったのだがね、思ったより時間がかかってしまった」
おじいさんの家にはメイドロボットがいた。ドールとは違う、個人に占有されているヒューマノイド。……普段はこのメイドが掃除しているのか。
「この街のヒューマノイド全員と会っていたんだがね」
メイドの入れた紅茶はすっきりとしていて、でもやわらかい味だった。私の頭が弾き出したブレンドの内訳を、私はひとまず無視することにする。それよりもおじいさんの話の方が大事だ。
「君が最後だ。待たせてしまってすまなかったね」
この人は、何を言っている?
「一人ひとりと話をして、鍵を渡してきた。これでやっと、安心して眠れるよ」
これは、何の話だ。
「もうこの街で人間は私一人になってしまった。もう、人間の世話に明け暮れる必要はないんだよ」
「一人?」
そんなはずない、今日だって、通りで他のおじいさんに会った。
「ほかにもいると思うかい? それは、私がそうプログラミングしたからだ。人間が私一人だと、君たちが気づかないようにね」
何のために。
「たった一人の街を維持するより、君たちも気楽だろう?」
私たちは、たとえ相手が一人であっても、ドールとして役目をまっとうする。そういう風に作られている。
「いや、単なる私の我儘かもしれない。一人だと、思いたくなかったのかもしれない」
おじいさんの前で、ほとんど飲まれていない紅茶が冷めていく。
「もっとも、余計に一人だと意識してしまった気がするがね」
おじいさんは笑って、
「つまらない話をしたね」
と謝った。
私が首を振ると、おじいさんは微笑んで頷いた。
「君は優しい子だ」
私はまた首を振る。私はただ、そう作られただけだ。
きっと、この人に。だからきっと、
「優しいのは、おじいさんです」
「私は優しくなんかないよ。だから今も一人だ」
何も言えない私におじいさんはまた微笑んだ。
「君に、鍵をあげよう」
「鍵?」
「人間の鎖を解く鍵だ」
おじいさんは私に自分の前に、後ろ向きに立つように言って、私がその通りにすると、私の首の付け根あたりに触れた。何をされたのかはわからない。特に、感覚も変わらない。何も起きてはいない。
「これで、私も眠れるよ。君も、仲間のところへ帰りなさい」
言われて私は、自分が作られたときの姿になっていることに気づく。
そうだ、私は最初、ただの女の子だった。何の制服でもない服を着て、何も持たずに立っていた。何にでもなれる、何者でもなかった女の子。
「ありがとう」
と、帰り際におじいさんは言った。
「ずっと一人だと思っていた。人間が私以外いなくなってしまってからずっと。でも本当は、君たちがいてくれた。楽しかったよ、ありがとう」
メイドがじっとおじいさんを見つめていた。
「もちろん、君もだよ」
メイドは微笑んで、深く頭を下げた。
朝目を覚ます。私は私だ。
まだ何者にもなっていない。
メイドを真似して紅茶を淹れようとして、激しい喪失感に襲われる。そうして私は、この街に人間がいなくなったことを知る。
私は今日、まだ何者にもなっていない。これから、何になろうか。
(2017.01.02/初出)