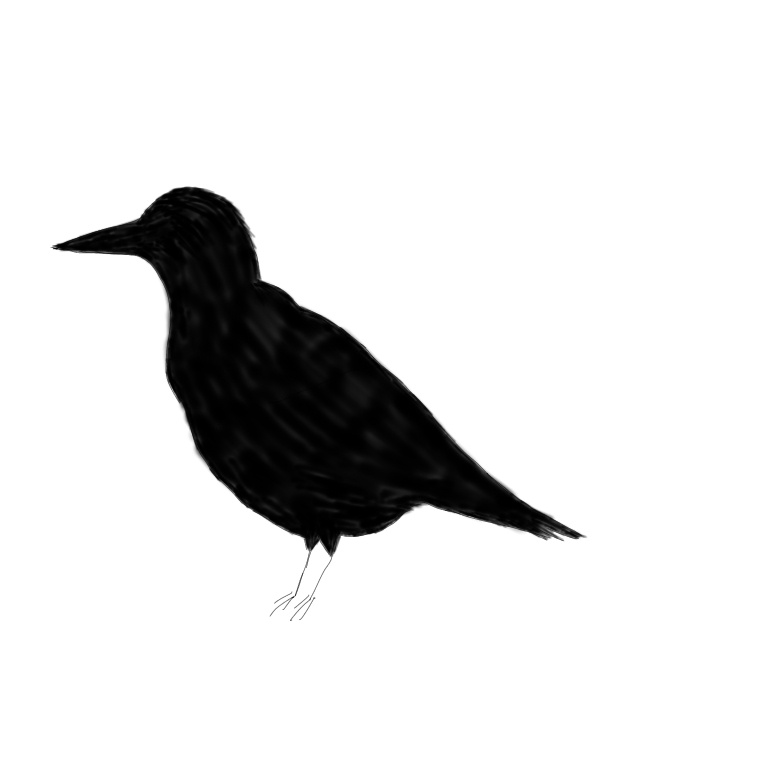職場のあるビルを出て歩き出したら海の匂いがした。
たしかにここも海の近くではあるけど、普段は海の匂いなんて感じない。都会の隙間の海は立ち並ぶビルやマンションの向こうで俺はいつもそこに海があることなんて忘れている。風向きだろうか。そんなことを思いながら駅までの長くない道を歩き続ける。ごく短い坂を上がると橋。橋の下では暗い緑の水がゆるゆると流れている……流れてるんだよな? あまりにも緩やかで、どちらに流れているのかもわからない。橋を渡り終えたら今度は下り坂。この辺りでは橋の両側が坂になる。地面が川より低いのだ。考えるともなしにそんなことを、つまり海の匂いとか坂とか地面の高さとか、そういうことを考えていたんだろう。ふと、少し前の休日のことを思い出した。
その日俺は電話一本で呼び出された。いまどき呼び出しといえばなんらかのSNSが主流のような気もするけど、生憎俺たちは電話番号とメールアドレスしか知らない。SNS、なんてものが登場する遥か前の知り合いで、携帯の電話番号とメールアドレスを知っているのもぎりぎりだ。俺たちの年代が携帯電話というものを持つことができたのは大抵はせいぜい高校生になってからで、俺なんて三年生も終わろうかという頃だった。……ああ、今はスマホだな。
はあ、はあ、と自分の切らす息が聞こえる。社会人になってから、否、高校を卒業してから、急な坂を、それもこんな距離上ったことはない。夏はもう終わりに近づいていたけど、猛暑の続いたこの夏はまだ暑い。坂を上っていると尚更だ。自分の息の後ろから、波の音が聞こえる。背中を押すように、坂の下から波の音が絶えず聞こえていた。夕方の坂道では誰ともすれ違わない。何もないわりに観光客にもそこそこ知られた場所だから、もっと人がいるものかと思っていた。観光客は夕方にはもうとっくに帰路についているのかもしれない。記憶の中では草がぼうぼうに生えていた坂の脇――崖とでも言うのだろうか――には家が建っていた。あの頃からずいぶんと年月が経ったのだと唐突に思う。
息切れしながら坂の頂上に着くと、中川と飯塚が手を上げた。
「ひさしぶり」
「体力ねえな」
「……なんでここなんだよ」
そこは俺たちが卒業した高校の正門前で、あまり待ち合わせに適した場所とは思えなかった。最寄り駅はそれぞれの実家の最寄り駅から単線の超ローカルな路線で何駅も離れたところだし、周りには特に何もないし、学校に勝手に入るわけにはいかないだろうし、ここで待ち合わせたところでどこへも行けない。
「いや、久々に坂からの景色が見たいと思ってさ」
「……ああ」
なんでもなさすぎる理由に項垂れつつもどこかで納得してしまう。高校は坂の上にあって、俺たちが通学に使っていた駅は坂の下にある。つまり坂からの景色は下校時の景色だ。坂からは線路より国道より、その向こうの海が見えた。緩やかな波しかない暗い色の海の向こうに水平線と空、左右に少し視線をずらすと島や半島や山が見える。……えらく鮮やかに思い出すもんだな、なんて思って振り返って、
「え、」
頂上からの景色は、記憶の中のものとは大分違った。
「俺たちもびっくりしたよ」
「ぜんっぜん見えねえじゃん、島とかさあ!」
二人の声にも答えず呆然としてしまうほど、そこから見える海は狭くなっていた。卒業後に坂の左右に立ち並んだ建物たちが視界を縁取っている。
「まあ、もう……何年だ、十四、五年? くらい経ってるからな」
中川の言葉で少し我に返った。しみじみするやら呆れるやら、俺たちは苦笑して、坂を下り始めた。坂を下りているときに見える景色も当然あの頃より全然狭くて、それはなんだかすごく寂しかった。
「ずっと変わんねえと思ってたんだけどな」
「そういうもんだよな、なんでか」
変わらないものなんてないのにさ、と言う中川の声は明るいけれど寂しい調子で聞こえた。
「なんでだろうな」
なんで、は、変わったことに対してじゃないんだろうと思った。変わらないと思ってしまうことに対して、だ。たぶんだけど。
踏切の手前まで下りるとようやく視界が開けた。
赤く夕焼け空が広がる下に暗い青色の海が揺れている。島も見える。電車が駅へと踏切を通過していった。つまり次の電車は十分後だ。二人にとっては十二分後か。俺と二人は反対方向の電車に乗った先に実家があって、高校生の頃は坂を下りて駅でどちらかの電車が来るまでが三人での時間だった。
「そういえば、海って行ったことねーな」
駅のベンチに座ると見るともなしに海を見る形になる。
海に向いたこの駅のホームから見えるもの――線路の向こうは国道で、その向こうは海。つまりここから見える景色は、ほとんど海とその上の空だ。
「たしかに」
その、三年間すぐそこにあった海に、俺は一度も行ったことがなかった。口振りから察するに二人もそうなんだろう。一年生のときにたまたま同じクラスでなんとなく仲良くなった俺たちは、毎日駅で落ち合って坂を上り、毎日一緒に坂を下って電車を待った。一年経ってクラスが変わってからもそれは続いて、結局三年間、球技大会の朝練や文化祭の準備以外でメンバーが欠けることはなかった。
「海も、変わってんのかな」
呟いた飯塚を振り向いたら、まっすぐ海を見つめていて、俺は一瞬、何を言うべきなのかわからなくなった。それで、仕方なくもう一度海を見た。
「変わってないように見えるけど、」
変わっているのだろうか。
俺が零した言葉はそんな普通のことで、でも誰も、聞き咎めたりしなかった。
「変わらないものなんてないらしいから」
中川の声は穏やかで、優しくさえあった。
そうだ。すべては変わっていってしまう。坂の周囲も、坂から見える景色も、見えないところだって、きっと。
「夏ももう終わりだしな」
季節もどんどんと変わっていく。
俺たちは高校を卒業し、毎日会うこともなくなり、ごくたまに電話やメールをしたりもっとたまに飲みに行ったりするだけになった。大学も卒業して、就職して、転職したりしなかったりして。
「平成も終わるんだろ」
「来年の春にね」
「なんか、変な感じだよな」
咄嗟によくわからなくて首を傾げた俺を見て、続ける。
「平成最後、って言われると、なんか特別な気がしてくるじゃん。別に俺ら平成生まれでもないのに」
最後、という言葉は、意味もなく感傷的にさせる、気がする。
「まあでも、これまで生きてきたのほとんど平成じゃん?」
中川が言って、俺たちは「まぁ、たしかに?」と頷くやら肩を竦めるやらした。
俺たちが物心ついたときにはもう時代は平成という名前だった。
「昭和生まれ、って言われるけどさあ」
俺たちに昭和の記憶はほとんどないと言っていい。
その、これまで俺たちの人生の大半がそうだった平成という時代は、来年には終わるらしい。
「べつに、平成が終わるから何、ってわけでもないんだけどな」
「俺はシステム対応があるよ……」
「ご愁傷様」
「縁起でもない言い方しないでくれ」
でもたしかに、時代の名前が変わるということについて、何を思うかと訊かれても俺たちは答えられない。俺たちが幼い頃から三十歳を過ぎるまで、年には西暦以外にそういう名前がついていた、それだけのことだ。
「時代って、こんな風に終わるんだな」
まじまじと顔を見てしまって、なんだよ、と言われる。
「同じことを思ってた」
「まぁ、そういうことだ」
俺と飯塚のやり取りに中川が妙に重々しく頷く。
急にあの景色が見たくなっていきなり呼び出したことの、それが理由なのかもしれなかった。
いつのまにか夕日はすっかり沈んで、ホームは白々と蛍光灯に照らされている。
そのうちに電車が来て、俺は二人と別れてそれに乗った。
そういえば二人はとっくに実家を出ているはずだけど、今日は実家に寄るのかもしれないし、あっちの終着駅で乗り換えて帰るのかもしれない。それはどうでもいい――悪い意味ではなく、どちらであっても構わないことで、ただ、まるであの頃と同じように別れたことがなんだかおかしかった。変わらないものも、たまにはある。
小さな電車はだんだんと、海から離れていく。
ビルの間を吹き抜ける風が冷たい。
夏は終わったのだ、と思った。
平成最後の夏――少なくとも俺にとっての平成最後の夏は、終わったのだ。
地下鉄の駅へ下りるエスカレーターに乗る。海の匂いは、いつのまにかしなくなっていた。
(2018.07.29/初出)