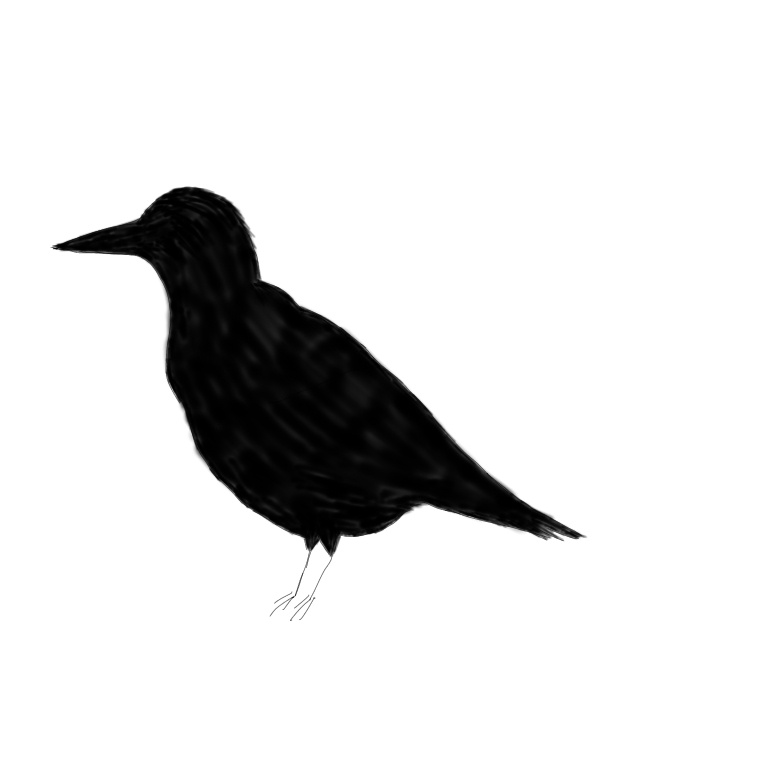今日も彼女は私の向かいで優雅にケーキを啄み紅茶を飲んでいる。十年前や二十年前と同じように。その姿は十年前とも二十年前とも変わらない。
ふと、横を見る。窓ガラスに私が映っている。
そうか。私はもう、彼女より年寄りになったのか。
十年前は彼女よりいくらか年下だったはずだけど、今では疑いようもなく彼女より年寄りな私がそこにいた。
彼女――大伯母は、コールドスリープ技術の治験のようなことをやっていて、十年に一度起きて私とお茶をする。私の前は祖母、つまり彼女の妹とお茶をしていた。彼女より年寄りになった祖母により私が彼女と引き合わされ、祖母が亡くなってからは私が面会もといお茶の相手を引き継いでいる。……はて、私も彼女より年寄りになったということは、そろそろ後継者を用意しなければならないのでは?
しかし困ったことに私には孫どころか子供もいない。
「どうしたの? 難しい顔して」
カップを置いて首を傾げる。
「や……歳取ったなあと思って」
「いやだ、コールドスリープしてても老けた?」
「そうじゃなくて」
自分のことだと言うと彼女も窓ガラスを見た。
「あら、ほんと」
……結構傷つくな。
「私の後、どうします」
「どうって?」
自分には子供もいないと言うと、彼女は「あらそんなこと」と言ってまた紅茶を飲んだ。
「そんなこと、って。保証人となる親族との面会はしなきゃダメなんでしょう」
このままでは面会以前に保証人がいないことになってしまう。私も親戚付き合いとかもう少しやっておくべきだった。
「そんな決まりまだあるの?」
変わったという話は聞いていない。
そう伝えると、彼女は盛大に溜め息をついた。
「そんなんじゃ、まだまだねえ」
何が? という私の顔を見て、でも何も答えずにまた紅茶を飲んだ。
「まだスキップが足りないわ」
コールドスリープで十年を過ごすことを彼女は「スキップする」と言う。
「……ずっと気になってたんですけど、」
私が言うと再び彼女がこちらを見る。
「どうしてコールドスリープなんてしようと思ったんですか?」
コールドスリープは眠りに就くそのときのまま、老化せずに眠り続ける技術だけど、まだ治験段階だ。極論、致命的なリスクもありうると説明されているはず。その技術に夢を見た人は多いだろうけど、実際にそれに身を投じたのは、そこに何か強い思いがある人ばかりだと報道では聞く。病気だけど長く生きたいとか、孫の成長した姿を見たいとか、夫の世話をせずに夫のいない老後を過ごしたいとか、とにかく長生きしたいとか、理由は何であれ、長命を強く望んだ人たち。――コールドスリープの治験に参加している人にはそういうイメージがある。
彼女はカップを置いて、何か考えるような顔をしていた。その顔には柔らかい笑みが浮かんでいる。
「約束したからよ」
「約束」
誰と、どんな。
「私たちが二人で生きていけるような社会になったのを見届ける、って」
いまいち飲み込めなかった。それが顔に出ていたのだろう、彼女は少し笑って、噛み砕くように言った。
「当時のこの国には、私たちが二人で生きていく手段がなかったのよ」
まあ今もなさそうだけど、と肩を竦めてまた紅茶を飲む。
結婚できないような間柄の恋人がいた、ということだろうか。祖母は大伯母についてほとんど説明してくれなかった。
「お相手の方も、コールドスリープを?」
入り込みすぎかなと思いつつも訊くと、彼女は首を振った。
「私がコールドスリープに入って四年目に亡くなったわ」
やや俯きこちらを見ないまま言った。
「病気だったの。当時の基準ではコールドスリープの対象にはなれないような。それで、貴方だけでも、って」
柔らかな微笑みは、寂しそうだった。
「相手の方も、独身を貫かれたんですか」
「いいえ?」
彼女の回答に驚く。そんな約束をするくらいだから、てっきりずっと恋人同士だったのかと思っていた。
「親御さんや周りの方を思ってね。優しい人なのよ」
「それでも、約束したんですか」
「ええ」
と答える顔が堂々と晴れやかな笑顔で少し戸惑う。
「病気がわかってからね、連絡をくれたのよ。嬉しかったわ」
よく病室でお茶をしたのよ、と幸せそうに思い出を語る彼女はまるで少女みたいだ。思い返してみると、さっき「どうして」と私に訊かれたときの顔は、考えていたのではなく、思い出していたのではないだろうか。幸せな思い出を。
お相手はどんな人だったのだろう。家柄のようなことかと思ったけれど、彼女の口振りは世間体や家の反対というより制度の問題のようだった。だとすると……、同性、とか?
「だから私は、まだスキップしなきゃ」
その言葉に引き戻されて彼女を見ると、彼女はこちらを見て微笑んだ。にっこりと、挑戦的に。
「ああ、でも、」
目を伏せる彼女につられて首を傾げる。
「こんな調子では、辿り着けるかしらね」
彼女の言わんとするところがよくわからなくて、私はまた首を傾げた。
「それまで、生きていられるかしら」
「そのためのコールドスリープでしょう」
歳を取らない眠り。文字通り十年をスキップできる技術。
どこかの企業の受け売りみたいなことを言ってみたら、彼女はふふ、と笑った。
「でもね、なんだか目が覚めるたびに前に目覚めたときより年寄りになっている気がするの。白髪や皺が増えて、脳細胞もスカスカになっていっているみたいな。鏡を見れば、特に変わってはいないはずなのに」
でも、どうしてもそんな気がするのよ。窓ガラスを見つめながら言う彼女は、私の目には初めて会ったときと変わっていない。その向かいにいる私はもう、彼女より年寄りだ。彼女が十年を一眠りで飛び越している間に、私は十年分しっかり老けた。
「それでも、またスキップするんでしょう」
「もちろん」
約束したんですもの。と笑う。
「あの人と一緒に生きていける世界を、少しでも見てみたいの」
それを冥土の土産にするのよ。
愛おしそうに、飲み干したティーカップを置く。
ふと、恋人とも限らないかもしれない、と思った。たとえば、友人とか。夫婦や親子でなくても、もしものときに病院についていけるとか相続できるとか、夫婦やいわゆる家族にならなくても共に生きていくことができるような制度は、少なくとも今のこの国にはない。
まぁ、私がどれだけ考えたところで真相は目の前の彼女しか知らないのだけれど。
「今日も美味しかったわ。付き合ってくれてありがとう」
にっこり笑って、彼女は施設へ戻っていく。また十年スキップするために。何度スキップした先で、彼女は自分たちの望んだ世界に出会うのだろう。
その世界を、私も見てみたいと少しだけ思ったけれど、私はまた、一人で暮らす自分の生活に戻る。スキップできない代わりに、せめて次の保証人を見つけなければ。保証人が必要な制度の是非はともかく、お茶の相手はいた方がきっといい、……いや、少なくとも彼女の望みが叶うのを見届ける誰かがいてほしい、これは私の願いだ。
(2021.12.31/初出)